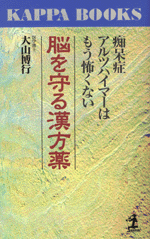前回までの記事
尿路結石と東洋医学(1)
尿路結石と東洋医学(2)
11.診断・鑑別診断
尿管結石では側腹部疝痛と肋骨脊柱角叩打痛を認め、顕微鏡的血尿、KUBで結石陰影を認めれば結石と診断してよい。
その後、超音波検査とDIPをとり確定診断する。
無痛生の尿路結石ではDIPをとり診断する。
右側の尿管結石でしばしば虫垂炎と誤診されるので要注意である。
また胃穿孔などの急性腹症との鑑別が必要である。
結石では腹部は平坦、軟であるのですぐに鑑別できる。
12.合併症
腎盂腎炎、膀胱炎を合併することがある。
結石性膿腎症では敗血症に陥ることもあるので、尿管ステント留置や経皮的腎瘻を造設し早急に尿の排液を計るべきである。
13.治療の原則・治療法の選択
大部分の結石(80%)は自然排石するので飲水や運動負荷により経過観察する。
短径8㎜以下の結石は自然排石するといわれている。
3か月以上結石が動かず、しかも直径が約1㎝以上の結石を手術対象とする。
第一選択が体外衝撃破砕石術(extracorporeal shock WAVE lithotripsy:ESWL)である。
しかし、ESWLの3か月完全排石率は約70%で、ESWL後の再発率は年率約10%であり、必ずしも万能とは言えない。
ESWLで大部分の結石は破砕されるが、骨盤腔内結石や硬い結石では経皮的腎砕石術や経尿道的尿管砕石術などの泌尿器内視鏡(Endourology)の適応となる。
Endourologyも不成功の症例に対してのみ観血的尿管切石術などを考慮する。
14.治療の実際
尿管結石に対しては、ウラジロガシエキス(ウロカルン6C/日)により自然排石を促す。
疼痛時はペンタゾシン(ソセゴン30㎎)、ヒドロキシジン(アタラックスP50㎎)を筋注する。
疼痛が強度の時は点滴にペンタゾシン15㎎を混ぜゆっくり滴下すると疼痛はおさまる。
自宅での鎮痛にはインドメタシン坐薬(50㎎)の頓用が効果的である。
無痛性結石に対しては泌尿器科医が適宜治療する。
15.予防法
予防の要諦は水分摂取にある。水分を摂取し、一日尿量を2L以上にするよう努めれば、再発頻度は減少する。
飲水による予防法が最も安価で容易であり、継続しやすい。
しかし、長期投薬による予防法もある。投薬による予防法としては、シュウ酸カルシウム結石予防にはサイアザイド系利尿薬(ダイクロトライド50㎎/日)、アロプリノール(アロプリノール100㎎/日)、ウラリット(クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合剤3g/日)など、尿酸結石予防にはアロプリノール(100~200㎎/日)、ウラリット(3g/日)を投与する。
まとめ
以上に述べたように、結石形成には複雑な要因がいろいろ絡まっていて、一筋縄では解決しない場合が多い。
しかし、丹念に原因を追求し、その原因を除去するように治療方針をたてれば、かなりの症例で解決が可能となる。
もし原因が不明であっても、飲水を促し飽食を避ければ、ある程度再発を予防できる。
再発予防の内服薬はあくまでも予防の一助であって、完全に再発を防止するものではない。
再発率を半分かそれ以下に低下させる手段に過ぎない。
ご相談はお気軽に

同じカテゴリの記事
- 漢方高貴薬・牛黄(ゴオウ)
- 精命力
- 高尿酸
- がんと乳酸菌
- 板藍根(ばんらんこん)
- ツボ豆知識(2)
- 腸内細菌とFK-23
- 茵陳五苓散(いんちんごれいさん)
- 「冷え性」によいツボ
- 糖尿病の人によい漢方薬
お悩みの症状から探す
- 子宝相談
(不妊症の悩みなど) - 心の病気
(うつ病、神経症、心身症など) - 皮膚病
(アトピー、乾癬など) - メタボの悩み
(肥満、美容、ダイエットなど) - 更年期の悩み
(更年期障害など) - 内臓の疾患
(脂肪肝、肝炎、肝硬変など) - アンチエイジング
(老化のスピードを緩めるなど) - 認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) - 女性の悩み
(生理不順、おりものなど) - 癌関連
(肝臓がんなど) - 体調管理
(疲労、熱中症など) - 関節の痛み
(膝痛、腰痛など) - 風邪の症状
(咳・鼻水・喉の痛みなど) - アレルギー
(花粉症など) - 眼疾患
(眼精疲労など) - 耳の不調
(耳鳴り・耳詰まりなど) - 毛の悩み
(抜け毛・薄毛など) - ペットの健康
(ペットの病気など)