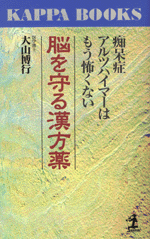はじめに
尿路結石は有史以前から存在することが知られている。
1901年、エジプトのAbidos附近のEI Amrah村落で、約7000年前の古代エジプトの古墳が発掘された。
中には子供のミイラがあり、その骨盤内に巨大な膀胱結石が発見された。
結石は帯黄褐色で表面が凹凸不整で顆粒状を呈し、結石の中心核部は尿酸であり、外被はシュウ酸カルシウムおよびリン酸アンモニウム・マグネシウムの混合結石であった。
このように古代では膀胱結石が中心であり上部尿路結石(腎結石、尿管結石)は少なかった。
このため、遊牧の放浪医が無麻酔で膀胱切石術を行い、死亡率は50%を超えていた。
中世には床屋外科医が床屋の傍ら膀胱切石術を施していた。
これも死亡率が高く、40~50%であった。
戦前の日本でも膀胱結石の方が多かったが、戦後、食の欧米化が進み高蛋白食を摂るようになって上部尿路結石が飛躍的に増加し、代わりに膀胱結石は激減した。
このような現象を結石波(stone wave)と呼んでおり、上部尿路結石は都会派に下部尿路結石(膀胱結石、尿道結石)は農村派に多いと言われているが、我が国ではすべて都会派と考えてよい。
1.疫学
本邦に於ける戦後の尿路結石の大部分(95%)は上部尿路結石であり、1975年の年間罹患率は10万人当たり53.2人であり、1995年の年間有病率は10万人当たり121.3人であり、増加傾向が続いている。
好発年齢は1965年には20歳台であったが、その後徐々に上昇し、最近(1995年)では50歳台に移行している。
男女比は2.4:1で戦前(6.9:1)に比べて女性の割合が増加している。
これらのデータは我国の全年齢層および男女の区別のない“飽食の時代”を物語るものであろう。
1995年の統計における生涯罹患率は、男子9.4%、女子4.1%であり、日本人男性の10.6人に1人が一生の間に一度は尿路結石に罹患することになる。
患者の発生は夏期に多く、冬期には少ない。
これは夏期には脱水のため尿が濃縮し結晶化が起こりやすいためである。
大都会ではカルシウム含有結石の比率が高く、地方ではリン酸アンモニウム・マグネシウム結石の比率が高いが、最近では地方の生活水準も向上したのでリン酸アンモニウム・マグネシウム結石の比率はどんどん都会に近づいている。
リン酸アンモニウム・マグネシウム結石は感染結石とも呼ばれ、下部尿路の細菌感染があると生じやすい。
2.病因
原因は60%が不明であるが、遺伝的要素も強く、結石患者の25%に家族が結石に罹患した既往歴があるという。
原因の明らかなものでは、高尿酸尿症(9%)、高カルシウム尿症(8%)、原発性副甲状腺機能亢進症(2%)などの内分泌代謝異常が26%である。その他の原因として尿流停滞(4%)、尿路感染(2%)、長期臥床(2%)などの環境因子(計8%)がある。
稀なものとしてアセタゾラミド(ダイアモックス)、副腎ステロイド、トリアムテレン、ケイ酸マグネシウム、インディナビルなどの薬剤による結石形成が知られている。
アセタゾラミドは緑内障の治療薬であるが、carbonIC anhydrase inhibitorであり、腎尿細管で重炭酸イオンの再吸収を阻害するため、尿中重炭酸イオンが増加し尿pHがアルカリ化する。
またリン酸尿(phosphaturia)をも同時に引き起こす。
リン酸カルシウムは尿pH>6.8で結晶化するため、この両者が相俟ってリン酸カルシウム結石形成を助長する。
副腎ステロイドは骨の脱灰を起こし尿中カルシウム排泄量が増し、その結果、カルシウム含有結石を生ずる。
トリアムテレン、ケイ酸マグネシウム、インディナビルは腸管で吸収された後、尿中に排泄され結晶化する。
3.結石形成因子
内分泌代謝異常、尿流停滞、尿路感染、長期臥床、薬剤による二次的なものなど種々あるが、要するに尿中のカルシウム、シュウ酸、リン酸、尿酸、アンモニウムなどの濃度が高くなり結晶が析出し、それ成長して結石となる訳である。
結晶が析出するには、各物質の濃度、尿のpH、温度、細菌感染など種々の要因が複雑に絡んでいる。
単に濃度が高いだけでは結晶は形成されない。リン酸カルシウムは尿pH>6.8で析出し始める。
シスチンや尿酸は尿pH>7で溶解度が急激に上昇する。
シュウ酸カルシウムは尿pHにあまり影響されないなど、結石の構成成分によってその性質は千差万別である。
故に、その患者に合った結石予防薬を投与する必要がある。
Proteus mirabilis,Klebsiella pneumoniaeなどのウレアーゼ産生細菌(urea‐splitting organism)の尿路感染があると尿素が分解されアンモニアを生じ、尿pH8を超えるようになりリン酸アンモニウム・マグネシウム結石などが形成される。
宇宙飛行士は長期間無重力状態に置かれるので骨に荷重がかからず、脱灰が生じ骨からカルシウムが溶出し、尿中カルシウムが上昇することによりカルシウム含有結石が生じやすい。
同様に、寝たきりの老人では骨のカルシウムが脱灰し膀胱結石などを生ずる。
シスチン尿症は常染色体性劣性遺伝疾患で、尿中にリジン、アルギニン、オルニチンなどのアミノ酸とともにシスチンを大量に排泄する。シスチンは最も難溶性アミノ酸なので、六角板状結晶を生じ結石となる。尿をアルカリ化する代謝性疾患として遠位尿細管性アシドーシス(RTA typeⅠ)があり、常染色体性劣性遺伝によるといわれている。
4.結石形成阻止因子
クエン酸、マグネシウム、ピロリン酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸などが知られている。
これらは大部分、シュウ酸カルシウムの形成阻止因子であるが、ピロリン酸はリン酸カルシウム阻止因子である。
このほか尿中の高分子物質にも結石形成阻止作用を持つものが多い。クエン酸はカルシウムをキレートすることにより結石形成を阻害する。
5.食事・supplement
古代や戦前のように低蛋白・低脂肪食を摂っていれば腎結石や尿管結石などの上部尿路結石を生ずる可能性は非常に低くなる。
その反面、膀胱結石や尿道結石などの下部尿路結石が増加する。
昔は尿酸アンモニウム、リン酸アンモニウム・尿酸、シュウ酸カルシウムなどを主成分とする膀胱結石が多かった。この中で尿酸結石のみが富裕層の結石で他の成分は農民や貧困層で見られた。
戦後は高蛋白・高脂肪食となり上部尿路結石が俄然多くなった。一般に肉、チーズ、牛乳を摂取すれば尿中のカルシウム排泄量が増加しカルシウム含有結石が増えると考えられている。
しかし、1993年、Curhanらが45,000名の成人男性を追跡し、食事によるカルシウム摂取が平均1,326㎎/日の群(高カルシウム食)は平均516㎎/日の群(低カルシウム食)に較べて有意に結石再発率が低く、牛乳をたくさん飲む群の方がほとんど飲まない群よりも再発率が低かった。
また、カルシウムをsupplementとして摂った群では摂らない群に対して有意に結石再発率が高かった。
Curhanらの言うことが正しければ、平均的日本人はカルシウム摂取量が500㎎前後であるので、日本人の多数で結石ができなければならないがそうでもない。
どうも言わんとするところは食事で摂ったカルシウムや牛乳は結石発生にはあまり悪さをしないが、supplementとして摂ったカルシウムはそのまま尿中に排泄されて結石形成因子となるということであろう。
この説は一見逆説的ではあるけれども、食事として摂ったカルシウムはリン酸などと必ず結合しているので、無闇に腸管で吸収されない。カルシウムもリン酸も腸管で吸収される時はフリーのイオンとなっていなければならない。
これに対してカルシウムsupplementはイオン化したカルシウムとして腸管に接するので容易に吸収され、ほとんどが尿中に出てしまう。
同様にビタミンDは腸管でのカルシウム吸収を促すが、余剰のカルシウムは尿中に排泄される。
これらのsupplement服用の際、カルシウムと結合するリン酸塩や硫酸塩が服用されたカルシウムに比べて圧倒的に少ないため、カルシウムと結合できず、余剰のカルシウムは血中へと吸収されてしまう。
シュウ酸に関しても同様で、ホウレンソウやチョコレートなどのシュウ酸を多量に含む食物を摂取しても、食物中ではシュウ酸はカルシウム、マグネシウムなどと結合しており、あまり腸管から吸収されず、その上、摂取されたシュウ酸の約半分は腸内細菌によって分解されてしまう。
故に、尿中シュウ酸の80%は内因性(肝産生)で、そのうち40%はビタミンC由来、40%はグリシン由来である。
このような理由で、ホウレンソウをお皿に山盛りに食べた場合でも尿中のシュウ酸排泄量が少量増加するのみであり、尿中シュウ酸排泄量の10%のみが摂取されたシュウ酸を反映する。
このように内因性のシュウ酸が多いので、美容などでもてはやされているビタミンCの大量摂取はシュウ酸カルシウム結石の源である。ビタミンCを1日10g以上摂取すると結石形成の可能性が高くなる。
また、美容のため太り過ぎを防止する意味で小腸切除や小腸のバイパス手術をすると、吸収不良により腸管内に胆汁酸や脂肪酸が増加する。
この結果、摂取されたカルシウムが腸管内で胆汁酸や脂肪酸とミセルを形成し、腸管内におけるカルシウムとシュウ酸の比が極端にシュウ酸に傾き、シュウ酸が大量に遊離するためシュウ酸吸収が増加しシュウ酸カルシウム結石ができやすくなる。
ご相談はお気軽に

同じカテゴリの記事
- 漢方薬は、特に、 慢性化した病気に優れた効果を示す!
- 漢方薬養酒用高貴薬解説(1)
- 漢方薬「熄風薬(そくふうやく)」
- C型肝炎と乳酸菌
- 膀胱炎の漢方治療
- 精命力
- 喘息発作によく効く漢方薬
- 東洋医学について
- 腸内フローラ(2)
- 高尿酸
お悩みの症状から探す
- 子宝相談
(不妊症の悩みなど) - 心の病気
(うつ病、神経症、心身症など) - 皮膚病
(アトピー、乾癬など) - メタボの悩み
(肥満、美容、ダイエットなど) - 更年期の悩み
(更年期障害など) - 内臓の疾患
(脂肪肝、肝炎、肝硬変など) - アンチエイジング
(老化のスピードを緩めるなど) - 認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) - 女性の悩み
(生理不順、おりものなど) - 癌関連
(肝臓がんなど) - 体調管理
(疲労、熱中症など) - 関節の痛み
(膝痛、腰痛など) - 風邪の症状
(咳・鼻水・喉の痛みなど) - アレルギー
(花粉症など) - 眼疾患
(眼精疲労など) - 耳の不調
(耳鳴り・耳詰まりなど) - 毛の悩み
(抜け毛・薄毛など) - ペットの健康
(ペットの病気など)