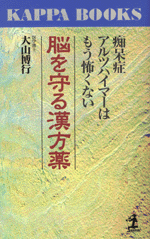1.高尿酸血症の定義と痛風の診断
(1)高尿酸血症の定義
血清尿酸値には著明な性差があることが知られている。
女性ホルモンには腎からの尿酸排泄を促進する作用があるために、閉経前の女性では男性に比して1~1.5mg/dl程血清尿酸値は低い。
しかし、閉経後には血清尿酸値は加齢と共に上昇し、次第に血清尿酸値の男女差は小さくなってくる。
治療ガイドラインでは高尿酸血症の定義として、尿酸の溶解度に基づいて性・年齢を問わず、血漿中の尿酸溶解度である7.0mg/dlを正常上限とし、これを超えるものを高尿酸血症と定義している。
老若男女を問わずに血清尿酸値が7.0mg/dlを超えたものを高尿酸血症としていることに注意していただきたい。
(2)痛風の診断
痛風関節炎は、以前から高尿酸血症を指摘されている患者の第1中足趾節(metatarsophalangeal:MTP)関節などに発赤、腫脹を伴う急性関節炎が出現した場合に診断できる。
診断基準はアメリカリウマチ学会のものがよく用いられている。
確定診断の上で重要なことは可能な限り腫脹関節より関節液を採取し偏光顕微鏡で観察し好中球に貧食された尿酸1ナトリウムの針状結晶を証明することである。
診断には以下の点に留意する必要がある。
1.痛風は高尿酸血症を基礎にもち、尿酸塩結晶の析出による痛風関節炎や痛風結節を来す疾患であり、診断にはその臨床的特徴が参考となる。
2.痛風の臨床的特徴
痛風関節炎は激烈な疼痛で突然に発症する単関節炎であり、圧倒的に男性に多い。
痛風関節炎の好発部位としては第1中足趾節関節であり、同部位に赤発、腫脹、圧痛、局所熱感を認める。
発作は24時間以内にピークに達し、通常7~10日で完全に緩解する。
3.痛風の検査の特徴
高尿酸血症は男女問わず、血清尿酸値が7.0mg/dlを超えるときに定義される。
関節液検査において偏光顕微鏡にて負の複屈折性を有する尿酸塩の針状結晶を認める。
尿酸塩を含んだ痛風結節を認め、骨・関節のX線検査において尿酸塩による骨破壊像であるpunched out像を認める。
4.高尿酸血症の病型診断
高尿酸血症の病型分類は表2に示すように、単位時間当たりの尿中尿酸排泄量から求められる尿酸産生量と、尿酸クリアランスから算出されるが、尿酸産生量が0.51mg/kg/時より高ければ尿酸産生過剰型、尿酸クリアランス(CUA)が6.2ml/minより低ければ尿酸排泄低下型と診断することになる。
5.痛風の鑑別診断としては慢性関節リウマチ、偽性痛風、感染性関節炎、蜂窩織炎、外反母趾などがあげられる。
2.痛風・高尿酸血症の治療
(1)急性痛風関節炎(痛風発作)に対する治療
痛風関節炎は疼痛が激しく、短期間ではあるが著しく患者のQOLを低下させる。
また痛風関節炎の経験は、原因となる高尿酸血症の長期治療へ導入する上でも重要であり、関節炎の沈静化をもって治療が終了したと考えてはならない。
痛風関節炎の治療としては、コルヒチン、NSAID、ステロイドの3種類の薬剤が用いられる。
コルヒチンは痛風発作の前兆期に少量のみ予防的に用いる。
発作極期にはNSAIDの短期大量投与が推奨されている。
ステロイドは経口投与や関節内投与などで用いられ、重症関節炎、多発性関節炎、NSAIDが使用できない腎機能低下患者などに使われる。
また痛風発作時に血清尿酸値を変動させると発作の増悪を認めることが多いため、発作中には尿酸降下薬を開始しないことが原則となる。
(2)高尿酸血症に対する治療
痛風・高尿酸血症の治療目的は、まず痛風関節炎の発作を防ぐことである。
さらに、高尿酸血症の合併症である腎障害(痛風腎)、尿路結石を発症、進展させないことはより重要となる。
また痛風・高尿酸血症には高脂血症、高血圧、耐糖能異常、肥満などの生活習慣病が高率に合併することが知られ、このような合併症が虚血性心疾患や脳血管障害の発症率を高くしていると考えられているので、血清尿酸値のコントロールだけでなく、合併症に対する十分な配慮も重要となってくる。
以上のことを踏まえて治療を行うが、血清尿酸値は6mg/dl以下のコントロールすることが望ましいとされている。高尿酸血症の治療指針を図5に示す。
(3)尿酸降下薬の選択
尿酸降下薬には尿酸生成抑制薬と尿酸排泄促進薬がある。
高尿酸血症はその成因によって尿酸産生過剰型と尿酸排泄低下型に大別されるが、前者には尿酸生成抑制薬を後者には尿酸排泄促進薬を使用するのが原則となる。
ただし、尿路結石の既往や保有例あるいは中等度以上の腎機能障害例には、尿酸排泄促進薬は尿中尿酸排泄量を増加させこれらの合併症を増悪させる可能性があるので好ましくなく、病型にかかわらず尿酸生成抑制薬で尿酸排泄量を抑制する必要がある。また現在使用されている唯一の尿酸生成抑制薬であるアロプリノールは、腎機能障害例ではその活性代謝産物であるオキシプリノールの蓄積性から副作用が起きやすいことが知られている。
これを避けるためには腎機能に応じてアロプリノール投与量を調節する必要がある。
尿路結石の予防には、低プリン食とアロプリノールを用いた高尿酸尿症対策に加えて、尿量を1日2000ml以上保つように飲水指導を行い、また食事療法と尿アルカリ化薬により尿pHを6.0~7.0に保つ尿路管理が重要となる。
(4)高尿酸血症を合併した高血圧の治療
最近の大規模臨床研究の成績から高尿酸血症が心血管疾患の独立した危険因子であることが次第に明らかになってきている。
本邦においても箱田らは1万人を越えるコホート研究から、血清尿酸値は男女において総死亡のリスクファクターであることを示し、男性においては8.0mg/dl以上、女性においては6.0mg/dl以上の血清尿酸値の群において、その後の総死亡の有意な上昇が認められたとしている。
また女性においてのみ血清尿酸値と心血管疾患死亡の間に有意な関連を認めたと報告しており、6.0mg/dl以上の血清尿酸値の群において死亡リスクの上昇を認めたと報告している。
また、特に高血圧患者においては高尿酸血症が心血管障害の独立した危険因子であることが一層明らかとなってきている。
血圧が良好にコントロールされた本態性高血圧患者を対象にしたWorsite Studyにおいて、心血管疾患(CVD)発症率(年齢と性で補正済み)は血清尿酸値と正の相関を示しており、血清尿酸値の低い群に比し高い群ではCVD発症の相対危険度は1.48であったとされている。これらの成績から血清尿酸値が男性で7.6mg/dl以上、女性で6.2mg/dl以上で心血管事故が増加すると報告している。
これらの点を踏まえて治療ガイドラインでは、高尿酸血症を合併した高血圧の治療チャートを示している。ここで尿酸が下がる降圧薬には?1遮断薬、ACE阻害薬、Ca拮抗薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬のロサルタンなどがある。
(5)生活指導
高尿酸血症の生活指導は、食事療法、飲酒制限、運動の推奨が中心となる。
ご相談はお気軽に

同じカテゴリの記事
- 不老長寿と漢方薬(1)
- 「非結核性抗酸菌症」と東洋医学(漢方薬・鍼灸・経絡ツボ療法)
- 女性の頻尿に効く漢方薬
- 「冷え性」によいツボ
- がんの再発・転移を考える(2)
- 二日酔い
- 月経のいろいろな異常(3)
- 糖尿病と漢方薬
- 修治附子末(しゅうじぶしまつ)
- 腰痛と漢方薬
お悩みの症状から探す
- 子宝相談
(不妊症の悩みなど) - 心の病気
(うつ病、神経症、心身症など) - 皮膚病
(アトピー、乾癬など) - メタボの悩み
(肥満、美容、ダイエットなど) - 更年期の悩み
(更年期障害など) - 内臓の疾患
(脂肪肝、肝炎、肝硬変など) - アンチエイジング
(老化のスピードを緩めるなど) - 認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) - 女性の悩み
(生理不順、おりものなど) - 癌関連
(肝臓がんなど) - 体調管理
(疲労、熱中症など) - 関節の痛み
(膝痛、腰痛など) - 風邪の症状
(咳・鼻水・喉の痛みなど) - アレルギー
(花粉症など) - 眼疾患
(眼精疲労など) - 耳の不調
(耳鳴り・耳詰まりなど) - 毛の悩み
(抜け毛・薄毛など) - ペットの健康
(ペットの病気など)