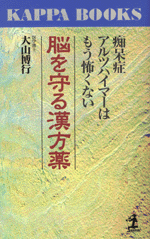前回の記事
尿路結石と東洋医学(1)
6.結石成分
シュウ酸カルシウム、リン酸カルシウムなどを主成分とするカルシウム含有結石が85%、リン酸アンモニウム・マグネシウム結石7%、尿酸結石5%、シスチン結石2%である。稀なものとしてキサンチン結石、2.8-dideoxyadenine結石などがある。
最近では赤外線分光分析で成分分析を行うので微量の結石の粉末があれば成分が判明する。
結石成分分析は今後の治療方針を決める重要な手掛かりとなるので、できるだけ尿中から結石を回収することが大切である。
7.病態生理
腎集合管で結晶形成が起こり集合管開口部でとどまり徐々に成長し腎結石となる。
この現象は多数の腎乳頭に同時に起こり得る。
ゆえに結石患者においては10年再発率が約半数となり、非常に高率となる。
腎乳頭にぶらさがった状態の小結石が成長し、何らかの衝撃を受けて脱落し尿管を閉塞する。
その結果、尿流が途絶し腎盂内圧が上昇し、疼痛を生ずる。
尿管は蠕動運動を繰り返すので周期的に痛む。これを結石疝痛とよぶ。
膀胱まで下降すればすぐに自然排石するが、前立腺肥大症などがあると膀胱にとどまり膀胱結石となる。
8.病理
腎結石には必ず核と臍が存在する。
核は結石の中心に存在し、シュウ酸カルシウム結石の場合はシュウ酸カルシウムまたは尿酸である。
核と被殻の成分は必ずしも一致しない。
被殻は何層にも層をなしており、その間に尿中の細菌や高分子物質が入り込んでいる。
臍は結石の腎乳頭部への付着部で凹んでおり茶褐色のことが多い。
ナイロン糸、針金、体温計などの異物を核として結石を形成することもある。
9.臨床像・臨床経過
尿管結石では突然の側腹部疝痛で発症する。
しばしば嘔気、嘔吐を伴う。
外陰部、下肢への放散痛を訴えることもある。
結石が膀胱付近に達すると残尿感や尿意頻数などの膀胱刺激症状が現れる。
膀胱刺激症状が出現すれば結石は数日中に自然排石する。
尿管結石ではときに肉眼的血尿を伴うことがある。
一般的に腎結石では痛みを生じない。
膀胱結石では排尿終末時痛、尿線途絶、血尿を主症状とする。
大部分の結石(80%)は自然排石する。
最も注意を払わなければならないのが症状を呈さない結石(silent stone)であり、一般に腎臓に嵌り込んでいる結石は痛みがない。
このため、長期間放置され腎機能が廃絶することがある。
疝痛発作は氷山の一角とみて慎重に精査すべきである。
10.検査所見
超音波で水腎水尿管症と結石エコー(acoustic shadow)を確認する。
腎尿管膀胱部単純撮影(plain film of kidney,ureter and bladder:KUB)、排泄性腎盂造影(drip infusion pyelography:DIP)を撮り水腎水尿管および結石陰影を確認する。
カルシウム含有結石はX線よく写るが、X線陰性結石(尿酸結石、シスチン結石、キサンチン結石、2,8‐dideoxyadenine結石、トリアムテレン結石、インディナビル結石、matrix結石など)では陰影欠損としてみられる。
一般にX線陰性結石であってもCT検査では白く写るので結石と判定できるが、インディナビル結石とmatrix結石(尿素分解菌などの細菌感染のある状態で粘液や細胞成分などが固まって泥状になったもの)はCTでも写らないので要注意である。
一般的に血算、血液生化学に異常を認めないが、原発性副甲状腺機能亢進症では血中カルシウムが高く、リンが低く、副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone:PTH)が高い。
ご相談はお気軽に

同じカテゴリの記事
- 民間薬(4)
- 病気の原因と東洋医学(漢方薬・鍼灸)
- 冷えてお腹が痛む人によい漢方薬
- 便秘と漢方薬
- 新型コロナウイルス感染症予防対策
- 不老長寿と漢方薬(1)
- 「気、血、水」のバランスが重要=東洋医学(漢方薬、鍼灸)の基本
- 漢方相談の実際 Q&A 「体は冷えるが首から上は暑い」
- 「冷える人」には「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」「人参養栄湯」「八味地黄丸」「温経湯」「当帰芍薬散」「人参湯」
- ツボ豆知識(2)
お悩みの症状から探す
- 子宝相談
(不妊症の悩みなど) - 心の病気
(うつ病、神経症、心身症など) - 皮膚病
(アトピー、乾癬など) - メタボの悩み
(肥満、美容、ダイエットなど) - 更年期の悩み
(更年期障害など) - 内臓の疾患
(脂肪肝、肝炎、肝硬変など) - アンチエイジング
(老化のスピードを緩めるなど) - 認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) - 女性の悩み
(生理不順、おりものなど) - 癌関連
(肝臓がんなど) - 体調管理
(疲労、熱中症など) - 関節の痛み
(膝痛、腰痛など) - 風邪の症状
(咳・鼻水・喉の痛みなど) - アレルギー
(花粉症など) - 眼疾患
(眼精疲労など) - 耳の不調
(耳鳴り・耳詰まりなど) - 毛の悩み
(抜け毛・薄毛など) - ペットの健康
(ペットの病気など)